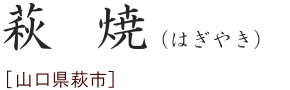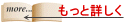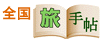 萩焼(歴史・特徴)
萩焼(歴史・特徴)
安土桃山時代、別名「やきもの戦争」とも呼ばれる「文禄・慶長の役」の後、大名・毛利輝元は、徳川家康により領地を減じられ、安芸の国から萩へ移封させられることになりました。その折りに、藩主とともに萩に移った朝鮮出身の陶工・李勺光(りしゃっこう)やその弟・李敬(りけい)らが中心となり、萩市の松本に御用窯(御用焼物所)を築き、本格的な作陶をはじめることになります。これが萩焼の創窯です。今からおよそ400年前のことでした。
「一楽、二萩、三唐津」という言葉があります。これは侘茶でいう優れモノの茶碗をランクづけしたもの。400年前に藩窯として誕生以来、萩は「茶の湯のためのやきもの=茶陶」の窯場として発展してきました。
典型的な特徴といえば、淡いビワ色や白色をした柔らかな焼き上がりで、使いこむほどに茶や酒がしみ込んで肌が変化するさまは「萩の七化(ななばけ」とか「茶馴れ」といわれ茶人に珍重されています。これは大道土(だいどうつち)という砂礫の多い地元産の土を、低下度でじっくり焼くことによってもたらされるもの。つまり、あまり焼き締まらず吸水性に富んでいるのです。
釉薬は土灰釉とワラ灰釉が主体です。白濁が濃いものが「白萩釉」や「白釉」、薄いものが「萩釉」などと呼ばれ、多くの作家や窯元で使われます。こうしてみると萩焼は意外とシンプル。一見、装飾性が乏しいとも思えます……。たとえば雑器の窯場などでは、素朴でも、装飾のバリエーションが豊かなものです。
けれど武士の茶の湯を背景に生まれたこのやきものは、多彩さよりも、土味の深さや芸術性が重視されたのでしょう。現在、萩では茶陶だけでなく食器も盛んに焼かれますが、こうした伝統は、作家たちの意識の底にしっかりと根付いているようです。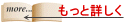 |
 |