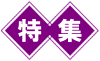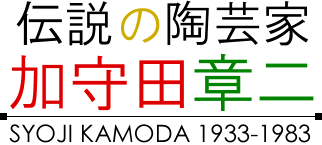|
|
| インターネット版 No.4 | 全2ページ 1 | 2 |
| 1 | ・特集 伝説の陶芸家 加守田章二 |
| 2 | ・とっておき WALKING POINTS ・・・ 小鹿田(おんた) ・加守田章二展 |
1/2ページ
|
||||
|
||||
| ●非凡な才能
|
|
| かつて日本橋のデパートで、加守田章二の個展が開かれていた頃のことです。 展覧会初日の早朝から、作品を求めるファンの列ができたといいます。 そして開店と同時に客は店内に雪崩込み、エレベーターでは遅くなるため、エスカレーターを使って一気に上階に駆けあがり、美術画廊へと向かったのです。 こうして競うように、新作が求められました。 これと同様のエピソードは、枚挙に暇ありません。 | |
 「変形筒彩陶」 高33.2 径18.3×11.2㎝ 1971年 |
 「曲線彫文壺」 高39.0 径9.0㎝ 1970年 |
偉大な創作家のキャリアには、幾つかの時代区分がある、といわれます。 そして、この陶芸家の軌跡を振り返る際にもそれが当てはまり、大別すれば益子時代(前期)と遠野時代(後期)に分けて見ることができます。 加守田章二は1933(昭和8)年、大阪府岸和田市に生まれました。 京都市立美術大学で陶芸を学び、卒業後は茨城県にあった日立製作所所有の大甕(おおみか)陶苑に就職しました。 このことが機縁となり、益子町を知ります。 そして、素朴で健やかな民窯の里で、いつの日か自由に仕事をすることを、夢に描いていたといわれます。 |
|
 「彩陶長方皿」 高7.7 径79.6×30.4㎝ 1971年 |
|
26歳の時、思い通り益子に独立するもしばらくは、生活が安定しませんでした。 なぜなら、当時の益子で主流だった民芸調とは一線を画した作品を焼いていて、地元の業者がほとんど仕入れなかったからです。 しかし非凡さは早くから窺え、次第に「益子の加守田」が世に周知されるようになり、作家としての地歩を徐々に築きつつありました。 とくに東京での初個展(1965年)では、見る者を魅了し、急速に多くのファンを獲得しました。 灰釉、鉄釉、土器風の作品など、そこには類い稀なシャープさや独創性、あるいは生命力がありました。 やがて、日本陶磁協会賞や高村光太郎賞など受賞を重ねながら、一方で銀陶、須恵器風の作品など、創作の手を決して緩めることなく、陶芸家としての絶頂期を向かえつつありました。 |
|
 「筒形彩陶」 高23.4 径12.8×8.3㎝ 1971年 |
 「彩色角扁壺」 高22.9 径20.5×11.5㎝ 1972年 |
| ●陶芸史に刻まれる足跡
|
|
| ところが一転、36歳になった1969(昭和44)年に、岩手県遠野市にも工房を建て、その翌年から、新工房における本格的な制作に着手するのです。
世間の喧騒から逃れて、ただ創作だけに没頭するための手段でした。 これが「遠野時代」のはじまりとなりました。 翌70(昭和45)年から遠野のアトリエで作られた作品が、東京で定期的に発表されるようになります。 曲線彫文、彩陶など、次々に作られる作品は、どのようにも形容しがたい陶器で、比類のない創造性があります。 そしてこれら一連の作品により、著しく高い評価を得て、「現代陶芸の旗手」などの異名を、ほしいままにしたのです。 これらの加守田作品(写真参照)は、伝統的な様式からかけ離れ、考えられない造形と装飾によって、見事に構築されていました。 しかも、独創的で斬新なのに独善には陥らず、見る者の心を打つ根拠が内包されていました。 色や形、パターンはもちろん、質感までにも、多くの日本人が共感したのです。 振り返れば、遠野時代の加守田章二は、陶芸家としての円熟期でもありました。 今ここで、日本の陶芸史に空前の作品を遺し、足跡を刻んだ偉大な作家の業績の一端を回顧することは、次代の日本の陶芸の姿を探ることに重なっていくのです。 |
| ※作品写真協力:陶芸メッセ・益子 ※なお本項は、「20世紀陶芸の神話 加守田章二展」(陶芸メッセ・益子)より取材し制作しました。 |