
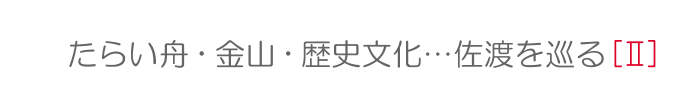


- 旅も中盤、いよいよ無名異焼の窯元へ
- 江戸時代に金山の町として栄えた相川町は、現在1万人弱ほどの人が住む、静かな落ち着いたたたずまいの町です。相川での金鉱脈の発見は、関ヶ原の戦いの翌年、1601(慶長6)年のことといいますから、今から400年前のこと。長らく江戸幕府の財政を支えたこの金山は無名異焼と切っても切れない縁があり、無名異焼誕生は金山なくしてはあり得ない! と言っても過言ではありません。そんな金山の麓に広がる相川の町を中心に今でも約25軒ほどの窯元が活動を続け、無名異焼の故郷として長い伝統を守り続けています。
 |
『現役登窯のある 数右エ門窯を訪問』 数右エ門窯は金山のそばに立ち茶器や酒器、茶道具から家庭食器まで幅広い制作をされている無名異焼の窯元です。釉裏紅の研究に陶芸人生を捧げた、初代数右エ門を父に持つ現当主・長浜数義氏に案内して頂きました。 |
 |
|
| 入口には無名異の土でできたおしゃれな風鈴が 飾られていました。 |
|
 |
金山によって繁栄を極めた江戸時代、相川では日用食器の需要が高まり、セトモノ屋も数軒あったといわれています。そのため日本海を北上していた北前船が、備前や越前焼など六古窯のやきものや、美濃焼、唐津焼や伊万里の器を積んで、続々と入港してきました。それにもかかわらず、佐渡では長い間やきものが焼かれることはありませんでした。佐渡で本格的な陶器製作が始まったのは、江戸後期の寛政年間(1789〜1800)頃。相川の黒沢金太郎が、本格的な佐渡生まれの施釉陶器をはじめて完成させたといわれています。その後、金山から掘り出される土を素地土に混ぜて、焼き始めました。これは釉薬を掛けずとも赤く焼き上がるのが特徴で、これが現在まで続く無名異焼の始まりです。 |
| 広々としたギャラリーに、数右エ門窯の作品が並べられています。 | |
 |
|
| 初代数右エ門は釉裏紅を得意としました。 残された作品は細かく絵付され見事な赤色を輝かせていました。 |
|
 |
突然の訪問にも関わらず、無名異焼について、その現状など長時間に渡りご説明頂き、改めて無名異焼の素晴らしさや、現状を知ることができました。 「7〜8年前まではアマチュアも含め40窯ほどあったが、今は25ぐらいになっている。観光客は多くなったものの、やきものが生活に行きわたり、観光で買う人が少なくなった」と語る2代目当主・長浜数義氏。一時期はお土産に無名異焼が飛ぶように売れて、島の窯元にゴールド・ラッシュをもたらしたといいますが、現在はどの陶産地も厳しい状況にあるようです。 長浜氏は武蔵野美術大学を卒業し彫刻を得意としているため無名異焼の他にもオブジェやアートな作品にも取り組まれています。 |
| 奥の床の間に飾られているのは氏がコレクションしている手ぬぐい。 その数と種類は趣味の域を越えるもの。 |
|
 |
|
 |
|
 |
|
 |
無名異焼と聞くと朱泥の焼締めの器を思い浮かべますが、実際は、練上げ手や美しいマリンブルーの施釉陶、または絵付の施された器や無名異土にこだわっていない焼締め陶など、窯元や作り手それぞれの新しい様式のやきものが次々に生まれています。 その背景には、京都の貴族文化、江戸の武家文化、それに西国の町人文化が渾然一体となって育まれてきた、この島の歴史・文化の特殊性があるといわれています。 当然ながら佐渡で生まれた陶器もそのような文化とともに発展してきました。まるで日本の陶芸界の縮図とでもいえるのが現代の無名異焼。そしてそれらの持つ多様な色や、いかなる形の器も、作者それぞれの志向と解釈によって作られている、どれも無名異焼なのです。 |
| ギャラリーに隣接した工房内に設けられた登り窯。 | |
 |
|
| 制作途中の作品が所狭しと並んでいました。 | |
 |
『水替無宿の墓から金山へ』 長浜氏のすすめにより、工房から続く裏山にある無宿人の墓へと向かいます。 思わず進むのがためらわれる道…この先に墓があるとのこと。道の険しさに加えて、真夏の照り返しも厳しくやっとの思いで到着。 |
 |
『普明の鐘』は金山での採掘作業などで亡くなった人の霊を鎮めるために鳴らす鎮魂の鐘です。 金採掘の作業はあまりに過酷で多くの人が鉱山の土になったといいます。 |
| 『普明の鐘』 | |
 |
|
| 墓石には坑内作業中に亡くなった218名の生国、戒名、名前などが刻まれています。 約1800人以上の人足(無宿者)が長崎の天領地から送られ、ほとんどがこの地で亡くなりました。 |
|
 |
|
| 「江戸」の文字が彫られた墓石。長崎の天領地以外にも、全国各地から相当数の人足が送らました。 | |
| 開山から約100年で、掘りつづけた坑道が海水面にまで達し、坑内の湧水に悩まされるようになります。江戸時代の金の採掘時の最難関が、坑に浸みだしてくるこの水の処理でした。『水替無宿の墓』の水替とはそうした坑道に入ってくる地下水を人力で掻い出す作業をいいます。水替には江戸などから強制的に無宿人を集め作業に当たらせましたが、あまりに過酷な作業のため、人夫たちはすぐに死んでしまったともいわれています。その霊を慰めるために建てられたのがこの墓でした。 | |
 |
水替無宿の墓から金山へはさらに険しい山道が続きます。 山道を抜けたところで茶屋を発見。冷たい飲み物にありつくことができました。 |
 |
『史跡佐渡金山』 写真右上に見える二つに割れた山「道遊の割戸(どうゆうのわれと)」は佐渡金山の象徴。金山開山当初から開発された最古の採掘跡の一つです。山頂から断崖絶壁を成すこのような採掘跡は世界的にも珍しく、国の史跡に指定されています。 |
| 茶屋から望む金山 | |
 |
掘り出された金鉱はベルトコンベアーやいくつかの小屋を経由して写真右側の棟まで運ばれトロッコで港へ、さらに船で瀬戸内海の工場へ運ばれたとのことです。 |
 |
|
 |
|
| 金山へと向う長い坂道を歩き始めたところ、声をかけてくるご老人が。話が始まると偶然にも三浦小平二氏の義弟、根本良平さんとのこと、なんとラッキーなことでしょう! 三浦小平二氏は人間国宝にも認定されている佐渡出身の有名作家です。金山まで向う途中、無名異焼のルーツなど詳しく伺うことができました。 | |
 |
『無名異坑跡』 道中にある、無名異焼の原料となった無名異坑跡を案内して頂きました。 金山から掘り出された鉄分(酸化鉄)を大量に含んだ赤色の粘土は、古くから止血剤や中風に効能のある薬に用いられ、佐渡でも薬用として販売されていたといいます。 |
| 金山入口へ向かう途中、階段を上がったところにあります。 | |
 |
「無名異焼は羽口(はぐち・金銀の精錬時に用いるフイゴの送風口)を作るために佐渡中の土を試験したものを閉山後、伊藤赤水、三浦常山により陶芸用として使うことで始まった」、さらに「江戸時代、金の鉱脈に付いている黄色い泥を三代常山が無名異と名付け、それを土に混ぜた」と教えて下さいました。 |
 |
炎天下、急な坂道を30分ほど歩き、ようやく金山入口が見えてきました。 佐渡金山は、1601(慶長6)年に金鉱脈が発見されて以降、江戸時代を通じて徳川幕府の財政を支えました。 百姓の寒村だった島には全国各地から労働者や鉱山技術者、商人などが集まり、人口5万人とも言われる大都市「相川」が誕生します。さらに、江戸と直結していた佐渡には、当時最先端の知識や技術がもたらされ、その後の日本鉱業界発展の礎となる多くの技術(火薬発破による採掘、削岩機など)が実用化されました。 展示室には創業当時の機械設備がそのままの姿で残されているので、歴史を物語る産業遺産を間近に見学することができます。 |
 |
|
 |
|
| 坑道隣には大規模な土産店があり、ここでも無名異焼が多数展示されています。 | |
 |
|
| 根本良平さんの作品も展示されていました。 | |
 |
『佐渡金山坑道入口』 坑道は「宗太夫抗(そうだゆうこう・江戸時代)」と「道遊抗(どうゆうこう・明治時代)」の2つ。開削された坑道の総延長は約400km(およそ東京−大阪間に匹敵)にも達します。 |
 |
開山した江戸時代から操業停止の平成元年まで388年間に採掘した金の量は78トン、銀は2,330トンにもおよんだそうです。 鉱山としての寿命がこれほどまでに長いのは世界でも珍しく、日本最大の金銀山となっています。 |
 |
明治から平成元年(1989)まで佐渡鉱山の大動脈として使われた「道遊抗」。機械工場、高任立坑(たかとうたてこう)などが見学できるほか、「道遊の割戸」を間近に見ることができる展望台が設置されています。 |
| 取材:2011年7月 |
| 無名異(むみょうい)焼 (新潟県佐渡郡相川町) |
|
| ◎金山(きんざん)の麓に点在する窯元
|
| 無名異焼・・・とは、なんだか聞き慣れない妙な名前のやきものです。 これは、新潟県の佐渡島において、江戸時代から現在までおよそ200年間に渡って焼き継がれてきた個性的な陶器です。 もちろん佐渡島はよく知られているように、北陸地方の北辺、日本海に浮かび、沖縄島に次ぐ日本第8位の面積を持つ大島です。 そして佐渡島といえば、なんといっても江戸幕府直轄だった金山(きんざん)や、民謡・佐渡おけさがとても有名です。 また最近では、国の特別天然記念物に指定されているトキの飼育の話題などで、たびたび全国的なニュースになっています。 さて、新潟港から佐渡島行きのカーフェリーかジェットフォイルに乗船すると、やがて船は両津港に接岸します。島に上陸したら今度はバスに乗り換え、1時間ほど揺られるといよいよ相川の町に着きます。 江戸時代に金山の町として栄えたこの相川町は、現在は1万人弱ほどの人が住む、静かな落ち着いたたたずまいの町です。 ことさら海の眺めが美しく、付近には多くの景勝地があり、とくにゆるりとカーブを描く七浦海岸や相川海中公園、雄壮な岩場や奇岩が続いていて飽きることのない尖閣湾の景観が見事です。 そしてこの辺り、相川町を中心にして多くの窯元が窯煙を上げ、無名異焼の故郷になっています。 |
| ◎無名異は漢方薬
|
| ところで、「無名異焼」という奇妙な名は、一体、どうしてつけられたのでしょうか。 もともと無名異とは、金山から掘り出された鉄分(酸化鉄)を大量に含んだ赤色の粘土のことをいいます。
こうした鉄の酸化物やマンガンを含んだ鉱物は、古くから止血剤や中風に効能のある薬に用いられ、佐渡でも薬用として販売されていたといいます。 そしてこの赤土の漢方薬としての呼称が、「無名異」だったわけです。
佐渡ではその無名異を素地土に混ぜて赤色の器を作ったから、「無名異焼」と呼ばれ親しまれるようになりました。 現在、島内にある窯元はおよそ40軒ほど。 その半数近くが相川町に集まっています。 町内を徒歩でぐるりと回ってみると、どの窯元にも「無名異焼」の看板が掛かっていますが、しかし展示されているものは、多種多様でじつに個性豊かなことに気がつきます。 どちらかというと無名異焼は、朱泥の焼締めの器のイメージが強いのですが、そればかりでなく、練上げ手があるかと思えば美しいマリンブルーの施釉陶なども見られ、または絵付の施された器や無名異土にこだわっていない焼締め陶など、窯元や作者それぞれの理解による、現在の佐渡島発の新しい様式のやきものが次々に生まれているのです。 その背景には、京都の貴族文化、江戸の武家文化、それに西国の町人文化が渾然一体となって育まれてきた、この島の歴史・文化の特殊性があるといわれています。 当然ながら器も、それらの文化と不即不離な関係を絶えず保ちながら、発展してきたのでしょう。 雅な絵付陶器が見つかったかと思えば、伝統的な朱泥焼締めがあったり、あるいはオリジナルな釉が特徴の器だったり、または無名異を単なる素材として用い、創作としての表現を追求している作品なども見られ、まるで日本の陶芸界の縮図とでもいえるのが現代の無名異焼の様相です。 そしてそれらの持つ多様な色や、いかなる形の器も、作者それぞれの志向と解釈によって作られている、どれも無名異焼なのです。 そんな中から好みにぴったりと合う器を見つけたり、またキラリと輝く若い才能を発見したりする喜びがあるのが、こうして実際に陶産地を巡る旅の最大の魅力といえます。 |
| ■無名異焼物語 |  無名異焼の代名詞ともいえるのが、この朱泥の急須です。 形も本当にいろいろな種類があって、どれにしようか迷ってしまいます。 「いいといわれるもの」を見つけようとするのではなく、「自分が気に入ったもの」を見つけて長く使い込めば込むほど、器肌にしっとりとした味わいが出てくるのが特徴です。 |
|
| ◎赤い器は佐渡の伝統
|
||
| 佐渡島・相川での金鉱脈の発見は、関ヶ原の戦いの翌年、1601(慶長6)年のことといいますから、ちょうど今から400年前のことです。 ほどなく幕府直轄の金山として召しかかえられ、長く江戸幕府の財政を支えました。 結局、平成元年までにこの島で採掘された金の総量は、なんと78トンにも及んだそうです。 そしてこの金山と無名異焼とは、ただならない因果関係によって強く結ばれていたのです。 江戸時代、金山景気に沸いていた相川の町には、日用食器の需要が高まり、セトモノ屋が数軒あったほどといわれています。 そのため日本海を北上していた北前船が、備前や越前焼など六古窯のやきものや、美濃焼、唐津焼や伊万里の器を積んで、続々と入港してきました。 それほど島での器の需要は多かったのですが、しかし長く佐渡産のやきものはありませんでした。 ようやく江戸後期の寛政年間(1789〜1800)頃になって、相川在の黒沢金太郎が、本格的な佐渡生まれの施釉陶器をはじめて完成させたといわれます。 佐渡島における独自のやきものの歴史は、ここからはじまります。 また次いで、金銀の精錬時に用いるフイゴの送風口(羽口)や瓦を焼くのを家業としていた7代伊藤甚兵衛が、文政年間(1818〜1829)頃、金山から掘り出される「無名異」(酸化鉄を含む赤い土)を素地土に混ぜて、茶器や酒器などを焼きはじめたといわれます。 これはとくに釉薬を掛けなくても赤く焼き上がるのが特徴で、これこそが現代にまで継承されている無名異焼の興りでした。 とはいっても、初期の頃の無名異焼は技術に熟達しておらず、まだ低火度でしか焼けなかったため、まるで楽焼のように柔らかな製品だったようです。 したがって日常生活で使えるような耐久性には欠けていて、残念ながら実用的な器とはいえませんでした。 しかし、無名異を利用した「朱もん」と呼ばれる朱泥の性質を活かした無釉焼締めの系譜は、そのまま佐渡のやきものの伝統となって、今日まで確かに生きながらえています。 |
||
| ◎飛ぶように売れる朱色の無名異焼
|
|||
| やがて徳川幕府は崩壊し、明治へと時代が移っていきます。 当然ながら、金山の経営も幕府から受け渡され、新たに明治政府直轄となって、近代的な合理化が急速に推進されました。
そしてやきものの製造にも、同様に近代化の波が押し寄せてきました。 各窯元ではそれら時代の要求に応えて、もっと量産ができ、より高火度で焼締められた耐久性のある無名異焼を作ろうとしました。 その先頭に立って精力的に活動したのが、常山(じょうざん)窯初代の三浦常山であり、また赤水窯の伊藤赤水(せきすい)がそれに続いていました。 そして明治6(1873)年になって、試行錯誤の末についに1200度もの高温で焼締めた本焼の無名異焼が完成しました。 「無名異焼」の名が定着したのも、この頃からだといわれています。 さらにこの時期には、作られるものに作家性が反映されはじめ、美術工芸品としての萌芽が見られる時代でもありました。 やがて常山窯や赤水窯から独立した人々が、島内各所に散らばって窯元となり、それぞれの無名異焼を互いに模索し発展していきました。 藁灰釉をかけた細工物や、絵付が巧みな器など、窯によって独自の工夫が顕著に現れはじめました。 |
|||
| しかし周辺地域の民のための器を焼くだけで、無名異の各窯元は経済的にはなかなか恵まれませんでした。 ところが昭和40年代になって、とくに1970(昭和45)年からはじまった国鉄(現JR)初のイメージキャンペーン「ディスカバー・ジャパン」に乗って、佐渡にも年間20万人という観光客が全国からどっと押し寄せてきました。
そしてお土産に無名異焼が飛ぶように売れだし、急須や夫婦湯飲みなど朱泥の茶器類が大ヒット商品になり、島の窯元にゴールド・ラッシュをもたらしたのです。 また無名異焼の朱泥急須は、急須の産地として世界的に知られる中国・宜興窯(ぎこうよう)のものと性質がよく似ていて、土の粒子がとても細かく、よって極めて硬質に焼き上がっています。 そのため無名異焼は、使い込めば込むほどに光沢が増し、一層の趣が器肌に現れるのが大きな特徴となり、多くのファンに長く愛玩されています。 |
|
||
| 取材:2001年 |

