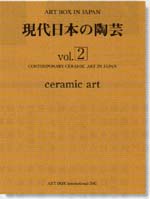わたしを呼ぶ≪アート≫
古代エジプトの棺からシャガールまで |
|
| 初代館長・松岡清次郎(1894-1989)は20代半ばより骨董に目覚め、半生をかけて2,400点余りの美術品を蒐集。美術品との出会いは、まさに一期一会。またオークションでは、一度に出品される品々は300~400点にものぼり、その数多くの美術品から自らの眼に適った作品を選んでいく。そうした幾度もの機会の中で、松岡は数点を取得することもあれば、関心を寄せるに至らなかったものも。美術品を選りすぐる判断基準は、あたかもコレクターが≪アート≫に呼ばれたかのようにも思える。開館50周年記念企画の第3弾は松岡の人となりに触れつつ、白金台移転後に紹介する機会のなかった作品も含めた幅広いコレクション展。 |
|
| 会 期 |
2025年 10月 28日(火)~ 2026年 2月 8日(日) |
|
| 会 場 |
松岡美術館
〒108-0071 東京都港区白金台 5-12-6
TEL:03-5449-0251 |
|
| 開館時間 |
10:00 ~ 17:00 ※第1金曜日は ~19:00
(入館は30分前まで) |
|
| 休 館 日 |
月曜日 |
|
| 入 館 料 |
一般:1,400円 25歳以下:700円
高校生以下:無料 |
|
| U R L |
:www.matsuoka-museum.jp/
|